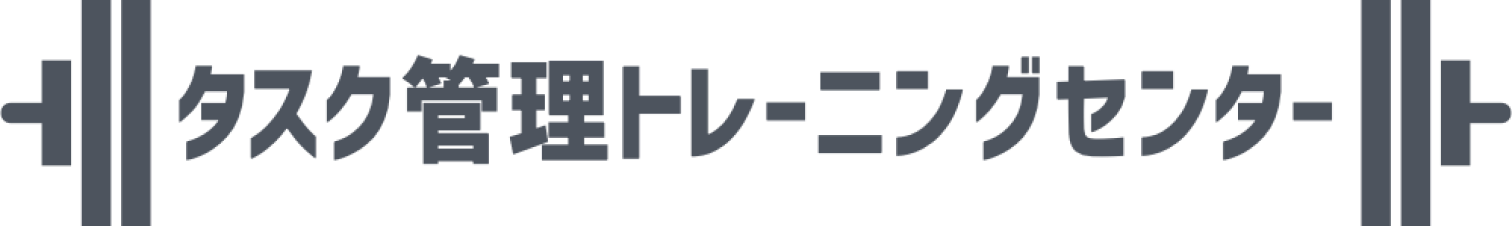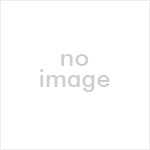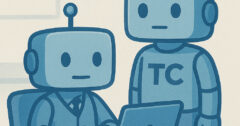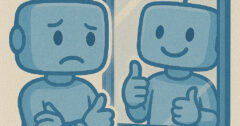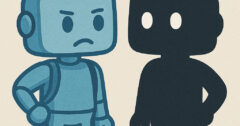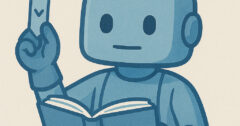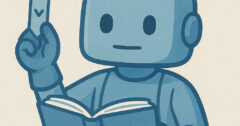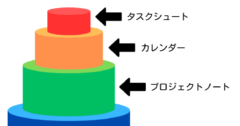「出直す」とは「最初からやり直す」という意味です。
とはいえ、僕にとってのこの言葉には字義通りの意味ではなく、特別な意味があります。
その特別な意味が付与されたのは2005年10月4日のことでした。
この日に「出直しの法則」というものに出会ったのです。
「出直しの法則」とは以下のようなものです。
社員が、出直しの法則を学び、仕事机の上、中にあるものすべてをいったん別の場所に移した。
そして、仕事を始めた。
まずはパソコンが必要になった。
彼の仕事のほとんどがそのパソコン上での処理だ。
電話を戻し、ペン一本とメモ用紙をもどした。
その日は、それだけでことがすんだ。
カレンダー、コップ、ウチワ、書類・・・、いつ、机に戻ってくるのだろう。
ウチワは来年の6月までは、きっと戻らない。
必用になったら戻す。
絶対必要なパソコンも、一度はずしてみたことが偉い。
前とすこし置く位置が変った。
経営にもまったく同じことが言える。
これは、榎本計介さんという経営者の方が書かれていたメールマガジンの一節で、2005年10月4日に配信されたものです。
実に20年前の記事ですが、その後も折に触れて読み返し、まさに「出直し」をしています。
ところでこの記事、タスクシューターの方であれば、一読してピンとくるはずです。
「ルーチンオールリセット」そのものだからです。
自分のスペースにあるモノをいったん外に追い出した上で、必要になる都度一つひとつ戻していく。
イチから出直すわけです。
ただ、この「出直し」は効果抜群なのですが、最初の一手である「リセット」がいきなり難易度が高い。
それゆえに、なかなか踏み出せず、代わりに「リセットせずに済むような小手先のテクニックでお茶を濁す」ことになりがちです。
当然ですが効果は限定的。
そうなると、最初の一手である「リセット」のハードルをいかに下げるかがポイントになります。
これについて考えてみます。